
第1回インターンシップ勉強会を終えて
前回「名古屋のIT業界を盛り上げるためのインターンシップ勉強会がスタート」という記事を書きました。
本日PART1として「企業のためのインターンシップ実施マニュアル」の第一章を読み感想などを共有しました。
そこで全員が共通した認識は「自分たちが考えていたインターンシップと違った」ということでした。
これが現在「学生」と「企業」の認識のずれの1つになっているのではないのではという第一章の中から導かれたものでした。
1、インターンシップとは
インターンシップとは、在学中に就業体験をすることで、就職活動は本来含まれていないというのがそもそもの始まりでした。
関係者は①大学(学生)②企業③行政です。
③の行政なんかは知らない方も多いのではないでしょうか。
私も知らなかったです。
2、単位認定される大学の多さ
実は大学では単位認定されるインターンシップが88%強実施されていると本の中で紹介されていました。
私は在学中そんなインターンシップがあるということすら知りませんでした。
事実実施率は25%強ということでした。
制度があるにもかかわらず利用されていないという非常にもったいない状況というのがこの本を読んでわかったことです。
3、学生と企業のニーズ
実際に当事者となるのが学生と企業です。
それぞれニーズがあります。
学生のニーズ
学生のニーズは現状就職活動の一環という立ち位置であることから、就職活動に有利に働くかどうかがニーズとなっています。
企業のニーズ
企業側のニーズも学生と同様、採用活動の一環となっています。
したがって採用できるかどうかがニーズになってきます。
企業も学生も「教育機会」とは考えていないのが現在のインターンシップとなっています。
インターンシップという言葉のマジック
現在TECHCAFEで触れ合う学生の多くは学習意欲が高い学生が多いです。
そのため学びの一環としてインターンシップをしてみたいというニーズがあります。
しかし先ほど書いた企業のニーズでは採用できるかどうかが大切になってきます。
そこで学生の企業の間でニーズが一致していません。
「採用」と言ってもアルバイトと正社員とあります。
創業間もない企業のインターンシップでは「採用」として「アルバイト」を求めていたりします。
その際、教育環境が準備できていなかったりするので、TECHCAFEの学生のニーズと合わなかったりします。
したがって私はインターンシップという言葉を使うべきかどうか再考する必要があるのではないかと考えました。
アルバイトの募集
飲食店でアルバイトをする学生は多いと思います。
その感覚でIT企業などでアルバイトとして業務を切り出し募集するというのがいいのではないかと考えました。
なぜならインターンシップでは人事部は成果を求められて教育の概念が抜けてしまいます。
そこでアルバイトとして雇用することで業務を教えるというサポートが必要だが、事業活動の一環として学生と接点を持てると考えました。
アルバイトを募集する企業を募集します
今回アルバイトを募集してみたい企業様のお話を聞いてみたいと思います。
どういう形ならアルバイトとして学生に実務経験を積んでもらえるか。
そして、学生に接点を持ち正社員雇用していけるか。
このようなことを一緒に考えることができたらと思っています。
もし興味をお持ちの企業様がいらっしゃればテックカフェまでお問い合わせください。



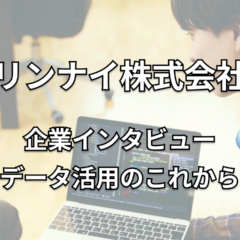

この記事へのコメントはありません。