
インターンシップ勉強会第2回を終えて
前回のDAY1に続き、DAY2の勉強会を行いました。
教材はこちら↓
DAY2は第2章を読んだ上での情報交換でした。
今回のメンバーはいつもと同じ、
株式会社SNAPSHOTの山森さんと株式会社プロトコーポレーションの新藤さんです。
第2章ではインターンシッププログラムの基本ということで、
「インターンシップの位置付け」や、「会社担当者に求められる」こと、そして「企業にとってのインターンシップ」という内容となっています。
インターンシップには、学生、大学、企業の3者が関係してきます。
この章では企業に割とフォーカスされた内容でした。
議論を経て現状のインターンシップにおける課題感は何か?
これまでTECHCAFEにお越しいただいた人事部の方などのお話や、学生のインターンシップの体験談などを通しての気づきにもなりますが、
企業と学生の間にギャップがある。
また、大学も学生のインターンシップには関与できていないということ。
この原因について考察した。
①企業がビジネス視点でインターンシップを捉え過ぎているのではないか?
企業はビジネス視点でインターンシップを捉えることにより、インターンシップを担当する人事部へ求める成果として「採用に繋がったかどうか」を求めすぎる。
もしくは、人が足りていないため、聞こえのいい「インターンシップ」という単語を使い労働者を確保する。
こんな側面が強く出ているのが現状のインターンシップなのではないか。
しかし、そもそものインターンシップとは、学生に就業の機会を設けることにより、キャリアを考えるきっかけにしたり、成長する機会とすることが目的であった。
そのため、ビジネス面を押し過ぎて、教育面の比率が少なくなってしまってい、学生との間でギャップが生まれているのではないか。
②学生のインターンシップに向けた事前学習が足りないのではないか?
一方学生の目線で見ていくと、インターンシップという聞こえのいい単語にとりあえず参加しておくかということで、事前に情報収集をあまりせず、理想と違ったということも起きているのではないかと考える。
現状大学の用意しているインターンシップではなく、自分で得たインターンシップの情報の中から参加する学生が多いように思う。
そこで、参加する前にインターンシップを参加することによるゴールなどの設定を特にすることもなく、またそのアドバイスをもらうことなく参加できてしまう環境になっている。
この辺りも企業と学生の間にギャップが生まれてしまう原因の一つではないか。
③大学も情報が多くなり、個々の学生の動きを追い切れないのではないか?
大学でのキャリア教育はどうなっているのか?
おそらく、学生がスマホなどで情報収集できるという点で、就職支援課を通さずインターンシップに参加していることが予想される。
現にTECHCAFEを利用している学生は就職支援課のような単語を出す者はいません。
そのため、事前学習するきっかけを大学側も提供しにくい外部環境になっているのが現状だと考える。
では我々は何ができるのか?
私たちのリソースは、ネットで情報を届けることができること。
そして学生と直にコミュニケーションが取れることにある。
そのため、インターンシップに参加する前に学生に対して事前学習の機会を提供することで、企業と学生の間にギャップが生まれにくい環境を提供できるのではないかと考えた。
また、メンターのような存在も学生には必要だと考える。
一方企業側へもアドバイザーとしてインターンシップを成功させるためのお手伝いも何かできるのではないかとも思っている。
この名古屋のIT業界を盛り上げるお手伝いとしてさらに勉強会を重ねて具体化していきたい。
さいごに
企業でインターンシップの開催において悩まれている方、ぜひ一度お話を聞かせていただきたいです。
TECHCAFEでは学生のニーズを聞くことができますが、企業のお話を聞く機会は限られています。
ぜひ情報交換をさせていただけたらと思います。
それではDAY3での学びも次回シェアいたします。
最後までお読みいただきありがとうございました。

![[野村尚克, 今永典秀]の企業のためのインターンシップ実施マニュアル](https://m.media-amazon.com/images/I/51tYltGx0yS.jpg)
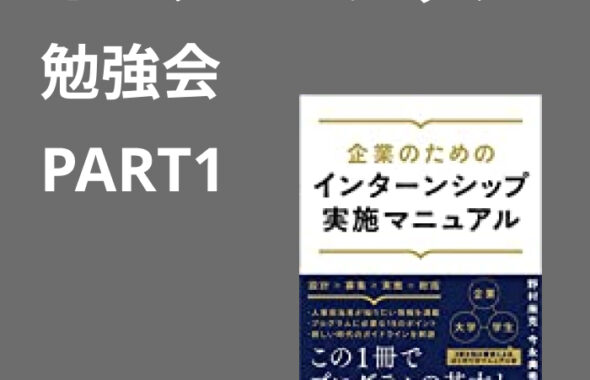

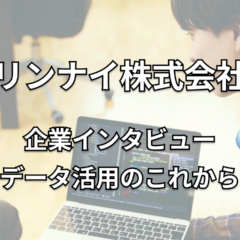

この記事へのコメントはありません。